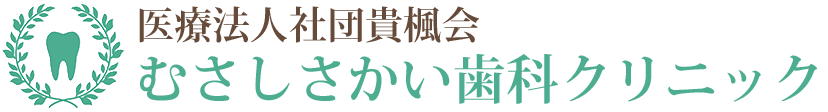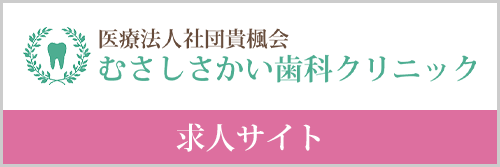武蔵境駅の近く、武蔵野市の歯医者・歯科医院
〒180-0014 東京都武蔵野市関前1-9-7 いなげや武蔵野関前店3階
JR中央線「武蔵境駅」北口より徒歩10分、またはバス「ひばりヶ丘駅」行きに乗車し約2分
西武新宿線「田無駅」よりバス「武蔵境」行きに乗車し約10分
駐車場:100台以上完備(いなげや駐車場)
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14:30~20:00 | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |
▲:14:30~17:00 休診日:火曜・祝日
当院のインプラント治療
※自費診療です
経験20年以上の院長が
治療を担当

インプラントを埋め込むあごの骨の周辺には、重要な血管や神経が走っています。インプラント治療はこれらの組織を傷つけずに処置を行わなければならず、高度な技術が要求されます。だからこそ、十分な技術や豊富な経験がある歯科医師が担当するのが理想です。
その点、当院では20年以上(※)の治療経験を持つ院長がインプラント治療をご提供しています。院長はこれまで数多くのインプラント関連セミナーに参加し、研鑽を積んできました。経験とノウハウを活かし、ご満足いただける治療に努めています。
難しい症例のインプラント治療を行えます
過去に別の医院でインプラント治療を断られてしまった方も、当院なら治療が可能なケースがあります。
インプラント治療ができない原因は、主に、インプラントを埋め込む部分に十分な骨がないことです。そのような場合、不足している部分の骨を増やす治療が選択肢として挙がります。しかし高度な技術を要する難しい方法ですので、実施できる歯科医師は限られていると言えるでしょう。
当院の場合、20年以上(※)のインプラント治療経験を持つ院長により、骨を増やす「GBR(骨誘導再生)」という治療を行うことが可能です。過去に「インプラントはできない」と言われた方も治療できる可能性がありますので、諦めずに一度ご相談ください。
※2023年現在
安心して治療を
受けられるための工夫

インプラントは患者さまのあごの骨に埋め込むものです。外科手術を伴うため、処置の際に使用するインプラントシステムにもこだわっています。
歯科医師の知識や技術はもちろん、治療に用いる製品においてもご安心いただけるものを使いたいと考え厳選しています。
そうして選んだのが、老舗歯科メーカーであるデンツプライシロナ社の「アストラテックインプラントシステム」です。このシステムを使った治療は世界的にも症例数が多く、信頼性が高いと言えます。
インプラントは体に入れるものだからこそ、家電のように新しいタイプが良いとは限りません。長い年月の中で安全性や信頼性が証明されたもののほうが、より安心して提供できると考えています。
院内感染を防ぐ工夫

病院内で別の病気に感染してしまう「院内感染」がインプラント治療中に起きないよう、感染対策を徹底しています。
院内感染の原因は、治療に使用する器具の細菌汚染です。そのため歯科医師や歯科衛生士が使う滅菌グローブやマスク、ガウンなど、使い捨てにできる道具はなるべく使い捨てにしています。一度使ったものをほかの患者さまの治療に使い回すことはいたしません。
使い捨てにできない治療器具は、汚染の原因となる血液や唾液をしっかり洗い流した上で、入念に消毒・滅菌しています。
さらに、インプラント治療で使う器具をすべて個包装にし、ヨーロッパの厳しい審査をクリアした「クラスB滅菌器」を使って徹底的に再滅菌。これらの工夫が、ご安心いただける治療につながると考えています。
妥協のない
精密な被せ物を作製

インプラント手術の質や安全性に注力するのはもちろんのこと、当院では最終的な被せ物に至るまで一切の妥協を許しません。
手術の際は、人工の歯の根(フィクスチャー)を精密な角度・深さであごの骨に埋め込むのが大切です。加えて、患者さまがストレスなく食事や会話をするために被せ物(上部構造)も精密である必要があります。
そこで私どもは、被せ物の型どりを「プライムスキャン」という3Dデジタルスキャナーで実施。スキャナーによる型どりでは、従来のシリコン素材を使う型どりで起きがちなズレや変形がなく、土台にピッタリと合う被せ物を作製できます。また、スキャンデータをもとにコンピューター上で設計を行いますので、被せ物が精密に仕上がるのも利点です。
このように当院のインプラント治療は、すべての工程において一切の妥協なく治療を進めています。
最大5年の安心の保証制度

当院ではインプラント治療に対して5年間の保証期間をおつけしています。
インプラント治療は健康保険が適用されず自費診療となるため、保険診療と比べるとどうしても費用が高額になります。高い金額を支払ってインプラント治療を受けたのに、すぐに使えなくなってしまったらどうしようかと不安な方もいらっしゃるでしょう。そんなとき、この保証がトラブルが起きた際の安心材料になると考えています。
保証をご用意しているのは、私どもの自信の表れでもあります。ご満足いただける質を担保できると自負しているからこそ、責任を持って保証をおつけしているのです。
※保証が適用されるのは、当院で定期的にメインテナンスを受けている方に限ります。
インプラント治療
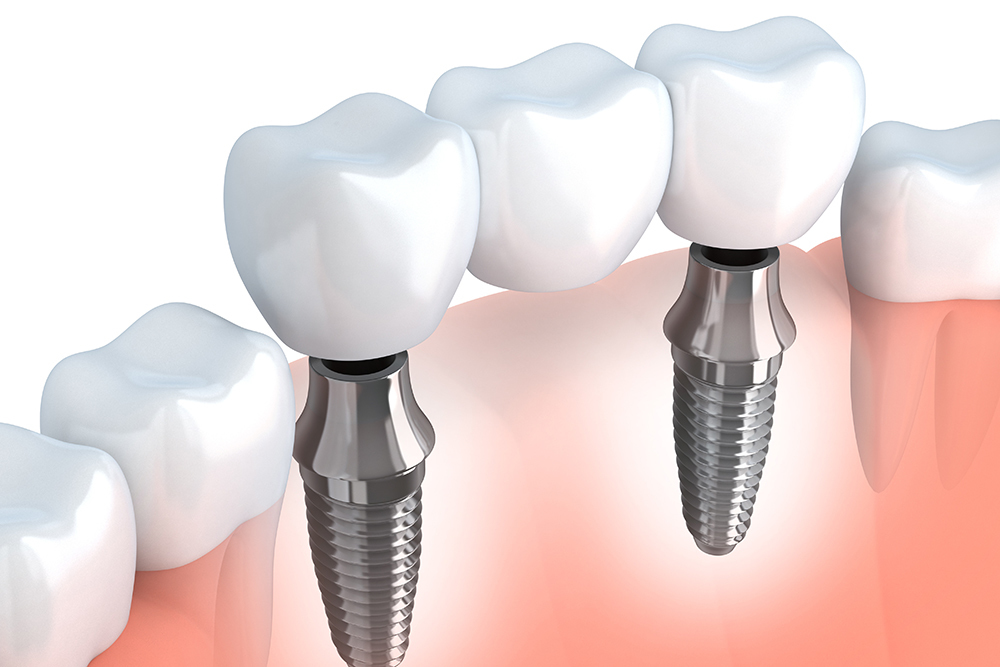
失われた歯のあごの骨に、人工の歯の根(チタン製)を埋め込み、その上に人工の歯(被せ物)をつける治療法です。
| インプラント治療 | 330,000~380,000円 |
|---|
治療の期間・回数:3~6か月
リスクや副作用:手術後に、痛みや腫れ、出血、合併症などを引き起こす可能性があります。噛む感覚がご自身の歯と異なる場合があります。見た目がご自身の歯と異なる場合があります。手術後にメインテナンスを継続しないと、インプラントが抜け落ちる可能性があります。
GBR(骨誘導再生)
インプラントを入れるには骨に厚みや高さが足りない場合に行う治療です。歯ぐきを切開し、骨が足りない部分に自分の骨、または人工の骨を注入し、メンブレンという専用の人工膜で覆って骨の再生を促します。
| GBR(骨誘導再生) | 55,000円 |
|---|
治療の期間・回数:3~6か月
リスクや副作用:手術後に、痛みや腫れ、出血、合併症などを引き起こす可能性があります。個人差により、予定量の再生ができない場合は再手術が必要になる場合があります。組織が再生するまで数か月の期間がかかります。
※金額は税込み表記です。
インプラント治療の流れ
インプラントの治療には、外科手術が伴います。手術はいくつかの方法がありますが、ここでは一般的な二回法(手術を2回行う)を元に、治療の流れをご説明します。
カウンセリング
インプラントの治療には、外科手術が伴います。手術はいくつかの方法がありますが、ここでは一般的な二回法(手術を2回行う)を元に、治療の流れをご説明します。

診査
診察・レントゲン撮影・全身の既往歴・骨の量などのチェックを行い、インプラント治療を効果的に行える状態かを調べます。

診断・治療計画
診査に基づき治療計画を立てます。症状や要望により、手術方法や使用するインプラントの種類・治療期間・治療費などが異なりますので、ここで詳しくご説明させていただきます。また治療前後にするべきことも含め、十分に検討して下さい。

手術前治療
必要であれば、インプラントを埋め込むことのできる口内環境に整えます。
虫歯や歯周病の治療や、不良な冠の除去、噛み合わせの治療などが必要です。また、歯槽骨が不足している場合は、骨造成などの治療を行います。
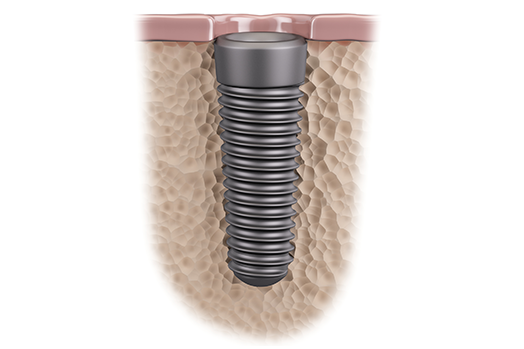
一次手術(インプラントの埋め込み)
清潔なクリーンルームにてインプラントを埋め込みます。インプラントを埋める部分の歯肉を開いて、顎の骨にインプラントを埋め込み、開いた歯肉を閉じて縫い合わせます。手術には体調や口内環境を整えて挑みましょう。また、投薬をされている方は主治医の指示に従って下さい。
手術に対する不安もあると思います。心配なことは医師に確認し、安心して手術を受けられるようにしましょう。
安全にインプラント埋込手術が行えるように、麻酔医が全身状態を管理し、安全で痛みの無い手術を行うことが可能です。
治療期間(約3〜6ヶ月間)
手術後、埋め込んだインプラントが骨と結合するまで安静期間をおきます。症状や治療内容により異なりますが、約3〜6ヶ月ほど待ちます。また、この間必要に応じて仮の歯を入れますので日常生活に支障はありません。

第二次手術(インプラント上部構造のセット)
インプラント体を歯肉の下に埋め込んだ状態で骨との結合期間を経てから、アバットメントを取り付け、人工の歯が接続できるようにします。
インプラントの冠は全体的なバランスをみるため、場合によっては仮の歯をセットします。噛み合わせの状態をチェックし、お口の中でバランス(調和)が整った時点で型をとり、色や形を患者さんに合わせて人工歯を作製します。

人口歯の取り付け
噛み合わせの調整などが済んだら、人工歯を取り付けます。万が一、ここで違和感などを感じたらすぐに医師に伝えましょう。

メンテナンス
上部構造を装着して治療は完了ではありません。
実はこれからが長く、大変な道のりなのです。天然の歯が歯周病にかかるように、清掃状態が悪ければ、インプラントも周囲炎といって、歯周病のような状態に陥ります。これを防ぐために、基本的に4ヶ月に一度来院していただき、状態のチェック・清掃を行っています。
診療時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |
午前:10:00~13:00
午後:14:30~20:00
▲:14:30~17:00
休診日:火曜・祝日